前回は「オンラインで会話の授業、どうやってる?」というタイトルで、「会話授業」について解説しました。
今回は、マスターテクストアプローチを使った授業について、もう少し詳しく解説していきたいと思います。
なぜマスターテクストアプローチ?
そもそもなぜ私が「マスターテクストアプローチ」に注目しているのか、その理由をお伝えします。
オンライン授業と相性がいい
まず一つには、オンライン授業とマスターテクストアプローチの相性がいいからです。
逆に言うと、オンライン授業と文法積み上げ式の総合教科書は相性が悪いと言えます。
※あくまで私の個人的な意見です。
一般的な文法積み上げ式の教科書は、学校で、毎日4時間、週5日、学習する人(いわゆる留学生)向けに作られています。
仮にそうでなかったとしても、初級修了までには約300時間かかると言われています。
300時間というと、1日4時間勉強したとしても75日かかり、週5日勉強したとしてだいたい15週間です。
つまり1日4時間週5日勉強する学習者が、初級を終えるのには約4ヶ月必要だということです。
毎日勉強してそれですから、週1回や2回のレッスンしか取れないオンラインの学習者さんでは、どうなるでしょうか…?

半年学び続けたのに、簡単な日本語も話せない…。

1年かかっても、初級教科書1冊も終わらない!
このように、オンライン授業で文法積み上げ式の総合教科書を使うと、時間がかかりすぎる上に学習者も成長を実感しずらいというデメリットがあります。
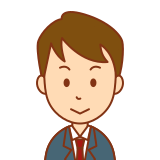
教科書を全部扱うと時間がかかるので、必要最低限の部分だけを選んでやろう!
と思う人もいるかもしれませんが、教科書は経験豊富な教師や研究者、編集者の方々が、長い時間をかけて作り上げたものです。
素人が勝手に間引いたが故に、文法が積み上がらなくなる危険性もあります。
教科書をアレンジするにしても、教師のスキルが必要なのです。
その点、マスターテクストアプローチのテキストは、基本的に1回完結型です。
それぞれの課にはそれぞれのテーマがあり、好きなテーマから学習することができます。
「積み上げる」必要もないので、比較的にどこをとっても授業をすることができます。
特に初級文法を一通り学んだ学習者が、会話の練習をするために使うのにはもってこいの教材です。
そしてオンラインの学習者さんには、そのような方が多くいらっしゃいます。
初級学習者でも話せる
2つ目のメリットとしては、学習者主体の授業ができるということです。
マスターテクストと呼ばれるモデル文がありますので、日本語初級者であってもそれを真似すれば、自分のことを話すことができます。
オンラインで学習する日本語学習者さんは、あまり学習時間の取れない方がほとんどです。
例え月あたりの学習時間が少なかったとしても、レッスン1回1回で話せるようになることが増える実感が得られることでしょう。
日本語を学び始めたばかりの方でも、ある程度のまとまった文が言えるようになるので、学習者は自信がつきます。
これらの理由により、レッスンへの満足度も必然的に高くなると思います。
今まで悩みにタネだった、「初級レベルだけど会話の練習がしたい」という学習者さんのニーズに答えることができます!
文法積み上げで起こりがちな、”初級が終わったのに話せない“という問題も、解決することができるでしょう!
教師の指導スキルに依存しない
そして、マスターテクストアプローチを使った授業は、「文法や語彙を教える」スタイルではなく、学習者の発話やアウトプットが中心の授業になります。
ですので「THE 文法の授業」のような、教師の準備や指導スキルも、それほど必要ではありません。
後に紹介しますが、マスターテクストアプローチで作られたいくつかの教材は、地域の日本語教室向けのものが多いです。
つまり、資格や知識・経験の(少)ないボランティア教師でも、ある程度教えることができるように作られています。
そのような教材を使うことで、教師は”授業“そのものに集中することができ、学習者とのコミュニケーションに焦点を当てた授業をすることができます。
幅広いレベル・ニーズに対応可能
マスターテクストアプローチを使ったテキストでは、教師のファシリテーション次第で様々なレベル・ニーズの学習者に対して授業を行うことができます。
基本的なマスターテクスト(モデル文)を使用しながら、その学習者に足りない部分や必要な練習を補うことで、カスタマイズされたオリジナルの授業にアレンジすることができるのです。
例えば、
- 内容確認問題を追加したり、答えを”書く”練習にする
- 文型練習のための問題を追加して、定着を図る
- 作文を書いて、ライティングのスキルアップ
- 作文や口頭発表を互いに評価するピアワーク
- 作文や口頭発表(録音)を宿題にして、自立学習につなげる
- 音声だけを聴かせて、聴解問題として扱う
- ペアワークを取り入れて、インタビュー(情報の聞き取り)活動に
- マスターテクストを穴抜きにして、ディクテーション問題に
などなどのアレンジが可能です。
教師のファシリテーションや授業の構成の工夫次第で、幅広いレベル・ニーズの学習者に対応することができます。
つまりそれは、学習者ごとに教材や教科書を変える必要がない、と言うこともできます。
さすがに、「初級・初中級」と「中級・上級」とを同じテキストでとはいきませんが、上級者には会話のテーマだけを拾ったり、架空人物のマスターテクストを作ってみるなど、応用できる部分は大いにあると思います。
マスターテクストアプローチのすすめ
- オンライン授業と相性がいい
- 初級の学習者でも話せる
- 教師の指導スキルに依存しない
- 幅広いレベル・ニーズに対応可能
以上の理由から、私はオンラインでの会話授業にはマスターテクストアプローチをおすすめします。
もともと私は、「今日の文法はこれです。この意味はこうで、活用はこう、例文はこれ、じゃあ練習問題やってみましょう〜」というような授業には、疑問を感じていました。
試験対策や”文型”を学びたい学習者にとってはいいのかもしれませんが、日本語でのコミュニケーション能力を育てることは難しいと思います。
また、そのような授業では、今や生身の教師に取って代わるコンテンツ(教科書や動画教材)が山のようにあります。
私のスタンスとしては、どんな言葉を使っても(言葉でなくても)、相手に伝えたいことが伝わればいいと思っています。
特に日本語初級者に対しては強くそう思いますし、この点に関しては日本人側ももう少し寛容になってほしいところです。
そうして、どんな形であれ「日本人とコミュニケーションが取れた!」という経験を積み上げることこそ初級学習者には必要なのではないでしょうか。
特にオンラインでは、趣味で日本語を学んでいるような方が多いです。
そのような方のモチベーション維持のためにも、そちらの方が楽しいのではないかと思っています。
↓この方の実体験にすごく共感したので、ここで共有しておきます。

教材一覧
マスターテクストアプローチを採用した教材は、今のところ以下の5つです。
NEJとその続編のNIJは、このアプローチを提唱されている西口先生が執筆されたものです。
千葉県国際交流協会作成の「わたしを伝える日本語」
特定非営利活動法人国際活動市民中心CINGA作成の「わたしをつたえるにほんご」
大阪府の作成の「きいて まねして はなしてーわたしたちが語る20のエピソードー」
東京都港区作成の「はなそう!みなとにほんご」
NEJとNIJ以外は、地域の日本語教室(生活者)向けに作られたもので、各公式サイトからそれぞれダウンロードが可能です。
私の個人的な感想としては、「きいて まねして はなして」が1番難しく(ボリューミー)、「わたしをつたえるにほんご」と「はなそう!みなとにほんご」が1番簡単(入門期から使える)のではないかなと思います。
実践例
ここからは、動画を使って私の実践例を紹介していきます。
あいさつ
こちらは「きいて まねして はなして」を使用した動画です。
このテキストの最初には、まずは基礎知識となる「パート1」があります。
マスターテクストを使用した本格的なレッスンになるのは、「パート2」からです。
「パート1」では、日本語初学者がまず最初に押さえておきたい基礎知識が紹介されています。
「パート1」では、
Unit1:あいさつ、自己紹介
Unit2:数字・電話番号
Unit3:時間
Unit4:日付
Unit5:お金
について学びます。
動画はUnit1しか作っていないのですが、いつか続きを…;;
買い物
こちらの動画は、実際にオンラインクラスで学習者を相手に授業をした際の録画です。
この時は、日本人の参加者も含めた複数人が参加するイベントでしたので、前の記事で紹介したスタンダードな授業方法とは少し違っています。
この時は8名くらいの学習者さんと、数人の日本語サポーターさんが参加してくれました。
※「日本語サポーター」とは、イベントで各ブレイクアウトルームでのファシリテーターを担当してくれる「あいうえお」のメンバーさんのことです。
語彙確認、マスターテクストの確認、リピート練習を全体で行った後、各ルームに分かれて練習・活動を行いました。
ちょっと昔すぎて、各ルームで何をしたのか覚えていないのですが…;
バラバラになったイラストを時系列順に並べたり、イラストを元にマスターテクストを復元したり、内容質問に答えたり、自分の買い物について会話したりしたんだと思います。
これならボランティアさんがたくさんいるオンラインの日本語教室などでもできそうですね(?)
こちらも動画内ではGoogle Jamboardを使用していますが、元データが見当たらなかったので、Googleスライドで作成したものを共有します。
必要な方はコピーして、お使いください。
自己紹介
続いてこちらは、「みなとにほんご」を使用した授業です。
2023年6月28日に行った、「実践実習コース」の説明会での模擬授業部分の録画です。
「そもそもマスターテクストアプローチって何?」という方向けの模擬授業です。
※学習者役は日本人です。
「マスターテクストアプローチはこうやれ」という決まった形があるわけではないので、アレンジ次第で色々な進め方ができます。
どんなテキストを使ったとしても、レベルやクラス形態が違えば、自ずと授業の進め方は変わってきますよね。それと同じです。
ですので一つの進め方や授業方法にこだわらず、色々な練習や活動を取り入れて、学習者に合った方法を見つけてください。
Q&A
先日「オンライン日本語教師サポートプログラム 実践実習コース」の開講にあたり、説明会を実施しました。
その際にいただいた質問をもとに、マスターテクストアプローチについて、もう少し補足します。

さらに上のレベルに対応しているテキストはありますか?
同時に、「どんなレベルの学習者に適しているか」というご質問もいただきました。
上記で紹介したマスターテクストアプローチのテキストを比べると、「はなそう!みなとにほんご」と「わたしを伝える日本語」が1番やさしいレベルだと思います。
CINGAの「わたしをつたえるにほんご」に関して言えば、外国語訳があるので、一番やさしいとも言えます。(英語、中国語、フィリピノ語、ベンガル語、ネパール語、フランス語、ベトナム語)
これらのテキストは、日本に来たばかりの日本語入門期の人でも使えるようにと設計されていたはずです。
※すみません、うろ覚えです:
一方で、「きいて まねして はなして」は、日本語初学者にはかなり難しいと思います。
それぞれの課に出てくるマスターテクストが結構長いので、必然的に扱われている語彙や文型も多くなります。
これを日本語知識ゼロの状態から学んでいくのは、かなりハードだと思います。
しかし逆に言えば、「きいて まねして はなして」は、初級修了者やある程度基礎知識がある学習者のアウトプット用教材としてはとてもいいと思います。
また、「きいて まねして はなして」の続編?として、「話して 書いて 伝え合う 私のこと・あなたのこと」という教材もあります。
こちらはグンとレベルが上がるような印象を受けますが、なかなかおもしろいテキストです。
いつか使ってみたいと思っています。
聞く・話す・読む・書くの4技能をスキルアップさせることができる、と謳われています。
※続編はマスターテクストアプローチで作られているわけではありません。
媒介語を使用しますか?
上で述べたように、マスターテクストアプローチのテキストのほとんどが日本語入門期の学習者向けです。
各課の初めには、スキーマ活性化のための質問があります。
例えば、自己紹介がテーマになっている課では、
というようなことについて、初めに学習者と話します。
これを日本語だけで聞いて日本語だけで答えてもらうのは、ほとんど不可能だと思います。
入門期の学習者を指導する場合には、媒介語やイラストなどの助けが必須になるのではないでしょうか。
本当に日本語ゼロの方を相手にする場合は、CINGAの「わたしをつたえるにほんご」にある外国語訳が役に立つと思います。
これらのテキストは、地域の日本語教室での使用を前提に作られているので、現場では辞書やGoogle翻訳の活用、学習者との媒介語があるサポーターが支援者になるなどの工夫が行われているのではないでしょうか。
オンラインでも同じことだと思います。
一人が一方的に話すような練習に、疑問を感じました。
確かにマスターテクストアプローチでは、会話ではなく一人一人の登場人物の「語り文」を練習していきます。
それはこのアプローチの目標が、学習者が「一人語りができるようになる」ことだからです。
テーマに沿って、まずは自分の話ができるようになることを目標として練習していきます。
自分が伝えたいことを日本語で言えるようになった後で、会話をしたり相手に質問をしたりすることにつなげていきます。
そのような会話や質問などの練習は、「活動」(アウトプット、アクティビティ、応用練習)として、それぞれの教師がオリジナリティを発揮できるところなのではないでしょうか。
実践実習コース

2022年11月から私は、「オンライン日本語教師サポートプログラム」を運営しています。
簡単に説明すると、オンラインで日本語を教えたい人のための養成講座です。
この度「オンライン日本語教師サポートプログラム」では、マスターテクストアプローチを使った会話授業の練習をする場所として、「実践実習コース」を開講します。
「実践実習コース」は、初任教師の圧倒的な経験不足を解消するための、授業の実践経験を積むコースです。
コース開講理由
初任教師の課題の一つとして、「やさしい日本語」が使えないということを感じています。
私自身は授業中に未習項目を使うことについて、それ自体は特別問題視していません。
コミュニケーションに必要ならば、その場で教えればいいと考えています。
しかし問題なのは、教師自身が「自分の発話が学習者にとってどのくらい難しいのか、または簡単なのか」を理解/把握できていないことだと思います。
つまり、自分の発話レベルをコントロールすることができていないのです。
その原因の一つには、教師が初級の学習項目の全貌を把握できていないことがあると考えます。
逆に言えば、日本語学習者はどのような順番でどのような日本語を習得していくのか、初級ではどのような漢字・語彙が扱われているのかが分かれば、このような問題は解決するのではないかと考えました。
しかし、初級のテキストを一通り授業できる機会が、誰しもにあるわけではありません。
そのための場所や学習者、長い時間も必要です。
それを解決するのが、マスターテクストアプローチです。
「文法積み上げではない」とは言え、扱われている文型は初級レベルですし、ある程度簡単なものから順番に並んでいます。
そのテキストを使って、10課や20課学習(授業)すれば、初級の学習項目を概観することができます。
※網羅することはできません。
そうすることで、初級の学習項目の全体像を把握し、語彙や文型のレベルをなんとなくでも把握することができるのではないでしょうか。
教授経験の乏しい初任教師でも、やさしい日本語が使えるようになる=自分の発話をコントロールできるようになるのではないかと考えています。
これが、私がこのコースでマスターテクストアプローチを使いたい、もう一つの理由です。
Q&A
ここで、説明会等でいただいた「実践実習コース」に関するご質問にお答えしていきます。

このコースで、媒介語は使いますか?
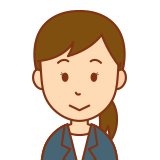
学習者によります。媒介語のスキルは必須ではありません。
このコースでターゲットとしている学習者は、初級修了者またはある程度の日本語の基礎知識がある学習者です。
今まで勉強してきた知識をアウトプットしたい=会話の練習がしたい、という学習者を相手に授業を行っていきます。
そういった方達には、それほど媒介語の必要はないと思います。
簡単な英語やイラストがあれば意思の疎通は可能でしょうし、その場でGoogle検索などをしていただいても何ら問題はありません。オンライン授業の特権ですね。
※コース外で日本語初学者に教える場合には、媒介語が必要だと思われます。

録画視聴のみでのコース参加も可能ですか?
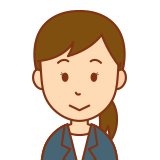
はい、問題ありません。
「まずは授業録画を見て学びたい」「フィードバックや授業検討会に参加して、他参加者から学びたい」「実際に授業をやってみたい」など、コースへの参加動機は様々です。
実践経験がゼロで、いますぐオンライン日本語教師としてデビューする予定もない、という方の参加も歓迎します。

教案や教材の作成は必要ですか?
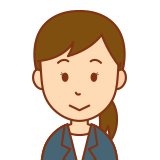
特に必要ありません。
テキストに沿って授業をやっていけば、基本的な授業はできるようになっています。
私は、「特別な教案も教材も必要なく、授業準備時間がほとんどいらない授業」を作ることも、これからの働き方として大切なことだと考えています。
それによって教師は、授業研究や教材研究、他の本当にやりたいことに時間をかけられるようになるからです。
そうしたサイクルを作ることで、教師の自己成長や自己実現につながり、「日本語教師の働きにくさ」に関する色々な問題も解決できると考えています。
ただし、例えば「ここでて形の練習をしたいから、説明・練習用の資料を追加したい」というようなこともあろうかと思います。
そういった場合には、教材作成していただくことは大いに歓迎ですし、テキストだけでは正直足りない部分もあると思います。
そこが日本語教師としての腕の見せ所であり、教師のオリジナリティが発揮できるところではないでしょうか。

「教材分析」では何をしますか?
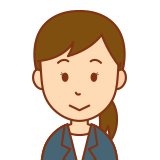
各課の読み合わせ、できる練習や活動のアイディア出し、文型の確認などを行います。
毎月、月初の全体ミーティングでは、「教材分析・授業検討会」を行う予定です。
自分がその月に授業を担当するかどうかに関わらず、課の内容を知っておくに越したことはありません。
内容を把握しながら、マスターテキストアプローチの活用方法を改めて考える時間にもしていただければと思います。
また、個人ではなくグループでその活動を行うことによって、様々な授業アイディアを得ることができると思います。
そこで出たアイディアや教材分析の結果は、録画ないしは資料(ドキュメントなど)にして、コース受講生全体で共有します。
コースに参加するには
「オンライン日本語教師サポートプログラム」全体の詳細については、こちらをご覧ください。
全部で4つのコースを設けてあります。
もう少し会話授業やマスターテクストアプローチについて知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください。
オンラインレッスンでの会話授業や、マスターテクストアプローチでの授業の進め方などについて解説しています。
「実践実習コース」は、月額会員制のサブスクリプションサービスです。
コースの人数制限はありません。
毎月第1週に全体ミーティングを行い、そこでその月の授業担当者を決定します。
基本的にはいつでも登録・解約が可能で、参加時以前の録画や資料も閲覧可能です。
ご登録を確認し次第、Discordコミュニティへのご案内をお送りいたします。
全体ミーティングまで、どうぞコミュニティ内のコンテンツをお楽しみください。
※「オンライン日本語教師サポートプログラム」は、文化庁の認可を受けているものではありません。コミュニティマネージャーが独自に開発し、個人的に運営しているものです。
※「オンライン日本語教師サポートプログラム 実践実習コース」は、マスターテクストアプローチ提唱者である西口光一先生や、先生の所属先である大阪大学・広島大学などとは一切関係ありません。
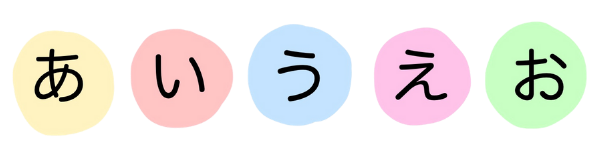
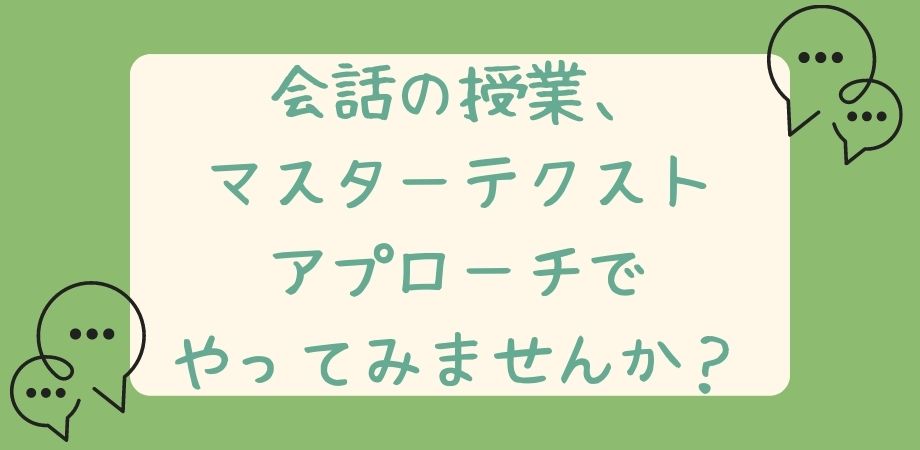
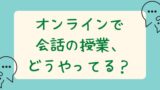












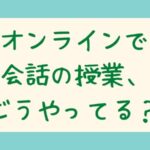
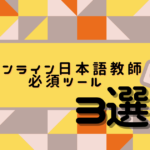
「初めて会った人と、どんな話をしますか?」